閉塞性動脈硬化症
閉塞性動脈硬化症についてご存じですか?
心臓の冠動脈や脳の動脈と同様に、足の動脈の壁にコレステロールという油分がたまり、動脈がつまってきて硬くなり(この状態を一般に動脈硬化と言います)、足への血の巡りが悪くなる病気を閉塞性動脈硬化症(ASO=Atherosclerosis obliterans)又は、末梢動脈疾患(PAD=Peripheral Artery Disease)と言います。
閉塞性動脈硬化症の原因
ASOになりやすい危険因子は、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患と同様で、高齢、男性、糖尿病、喫煙、高血圧、高脂血症(特に低HDL血症、高LDL血症)であり、メタボリック症候群とも密接な関係があります。特に、糖尿病の人は糖尿病で無い人に比較して、下肢切断が7倍の頻度で発生します。糖尿病を持たない人の大きな関節での切断の頻度は100万人当たり200〜280人ですが、糖尿病の人は頻度が高くて、100万人当たり3000〜3900人です。糖尿病のコントロールの悪い方(特に血中HbA1C(ヘモグロビン・エーワン・シー)の高い方は要注意です。
喫煙をすると、ASOの病態を悪化させ、跛行の増悪、下肢の虚血、切断、インターベンション治療を必要とすることとなります。
閉塞性動脈硬化症の症状
ASOの症状として、最も多いものが間歇性跛行です。
これは「歩くと足が痛く、重くなって歩けなくなり、休むとよくなる」というものです。他に足の冷感、シビれ、色調不良(灰色、黒色)などの症状もみられることが少なくありません。但し、脊椎菅狭窄症、糖尿病による神経障害などでも同様の症状がみられることがあります。
ASOでは、足に血を送る動脈がつまってきて血の巡りが悪くなるので、足の甲やつけ根で触れる脈が弱くなり、足で測定した血圧も下がります。このような状態を外来ですぐに調べることができるのがABIという検査項目です。これは足首の収縮期血圧を上腕の収縮期血圧で割って算出します。(これをABI=Ankle Brachial Indexと言います。)ABI検査では同時に、ASOによって血管がつまっているかどうかの他、動脈硬化による血管の硬さや血管年齢を知ることもできます。脊椎菅狭窄症や糖尿病性神経障害では、ASOと似た症状が出現しても、ASOはほぼ正常なので、この点で区別できます。

60歳以上の5%(男性)、2.5%(女性)にASOによる間歇性跛行がみられますが、ABI検査を用いれば少なくともその3倍の患者が見つかると思われます。間歇性跛行など自覚症状がなくとも、ASOはABI検査によって見つけられます。つまり、ABI検査をすると症状のほとんどない軽症のASOを早期に発見することができます。一般にABI=0.9以下がASO診断の基準値となっています。このABI=0.9以下を異常値として判定すれば、間歇性跛行などの症状があるかどうかを患者さんに尋ねる質問表を使った場合の約3倍の患者さんが見つかります。つまり、自覚症状が無いか又は軽い症状の多くの患者は、ABIが0.9以下となりますが、質問表では発見されません。すなわちABIは質問表よりも敏感なのです。
マルチスライスCTによる診断
以前は、動脈にカテーテルを挿入して血管造影を行なうことにより確定診断を行なっていましたが、マルチスライスCT(256列)の発達により、下肢の血管の状態も動脈にカテーテルを通すことなく造影剤の静脈内投与だけで全く安全に把握できるようになりました。マルチスライスCTは、ASO(PAD)の病変のスクリーニングにも最適で、ABIの次に行なうべきものです。
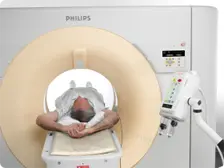
閉塞性動脈硬化症の治療方法
1.カテーテル治療
近年最も進歩しています。足の付け根から指の根本付近まで、局所麻酔下に多種の治療用具を用いる事により治療が可能。バルーン、ステント、レーザー、ロータブレーター等心臓の血管に対する治療法を応用できます。体に優しい治療です。特に、熱を発生しない“エキシマ・レーザー”では、従来治療が困難であった膝下の血管のみならず、足首から先の血管まで治療ができます。また、最新式のレーザー・ターボ・ブースターを用いると、レーザー治療がさらに有効となります。さらに、新しいタイプのステントを用いると、再狭窄(治療した箇所が再び狭くなること)を5〜10%以下に抑えることが可能です。

2.バイパス手術
運動療法に並ぶ古典的治療法。但し傷口も広範囲で大きく、また折角つないでも、その血管自体またつまってしまう事自体、稀ではありません。
3.血管再生療法
一部の施設で行なわれており、効果のあることが多いですが、種々の制約もあり全てのASO(PAD)の患者には使えません。
放置するとどうなる?
ASOの患者さんでは全身的な動脈硬化を伴っており、自覚症状の有無にかかわらず、心筋梗塞、脳卒中など心血管疾患による死亡の危険性が高くなります。少なくともASO患者さんの約30%が著しい冠動脈疾患、10%が脳動脈疾患を持っています。ASOの症状である間歇性跛行を持つ患者さんの死亡率は同じ年齢と同じ性の人と比較すると2-3倍です。ある研究では、ASO患者さんの5年後、15年後の死亡率はそれぞれ30%、70%で、ASOのない同年齢の高齢患者さんの死亡率は10%、30%でした。
ASO患者さんは75%が心臓か脳の疾患で死亡します。特に下肢切断術を受けた患者さんの院内死亡は17%、5年生存は50%以下です。ASOは、放置すれば、実は乳癌より長生きできない病気なのです。また、症状がなくても、ABIが0.9以下と異常値を示しただけで、放置すれば死亡率は、ABIが正常な人の3.8倍になります。
放置するとASO患者さんの16%(6人に1人)で症状(間歇性跛行)が進行し、25%(4人に1人)が手術を受けるか体の一部を失い、4%(25人に1人)近くの人が膝や足首など大きな関節を失うような切断術を受けることになります。フラミンガム研究によれば、間歇性跛行の有る患者さんで、4年間の間症状が変わらなかったのはわずかに30%でした。
閉塞性動脈硬化症の合併症
1.重症虚血肢
重症虚血肢とは、足への血流がほとんどなくなり、壊疽(腐ること)になっていく状態を指します。こうなると、足先の皮膚は、灰色から黒色をなっていき、潰瘍ができたりします。さらに細菌が感染して、熱が出たり、足が腫れ上がったりすることも少なくありません。また細菌が血液の中に入り敗血症の状態になると、すぐに生命にかかわる状態になります。このような状態を防ぐためには、足を切断せざるをえない場合が多くなります。ASOの患者さんのおよそ15-20%が間歇性跛行から重症虚血肢に移行すると推定されています。
2.虚血性心疾患
ASOが「足の動脈だけがつまって、血の巡りが悪くなる病気」と考えていてはいけません。ASOの死亡原因で最も多いものの一つが、実は、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患です。足の動脈はつけ根の最も太いところで1cm、太ももで5-6mm、膝から脛で2-4mm、足首から先は2mm位ですが、心臓の血管(冠動脈)は、その半分以下です。つまり、“太い血管がコレステロールでつまっていれば、より細い血管はもっとつまりやすい”ということです。ですから、「足の血管が相当つまっている状態なら、心臓の血管は当然つまっている可能性が高い」というわけです。もしASOが見つかったら、心臓の血管(冠動脈)も当然、検査するべきです。この心臓の血管の検査も、先ほどの256列マルチスライスCTで、簡単にできます。
3.脳血管障害
やはりASOを起こす動脈硬化が、足の血管、心臓の血管の他、脳の血管にも生じて起きるのが、脳梗塞(脳の血管がつまること)です。また高血圧を伴うことが多いので、動脈硬化で弾力性を失った脳の血管が破れて脳出血になることも少なくありません。




